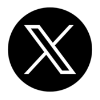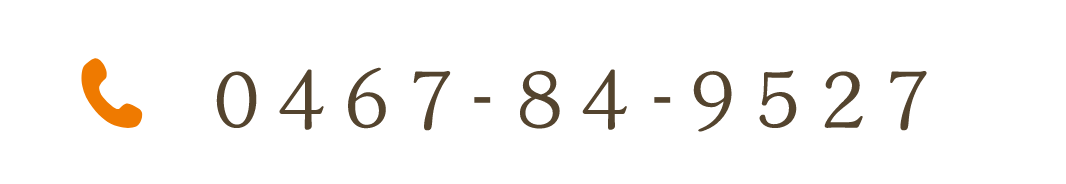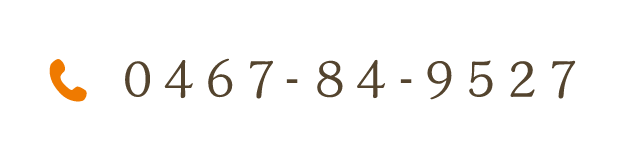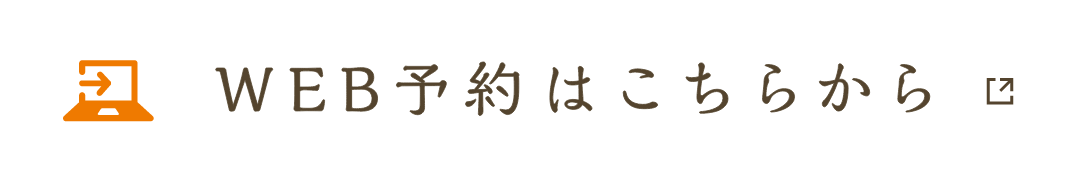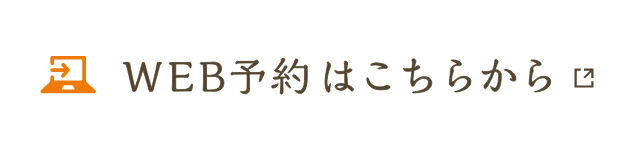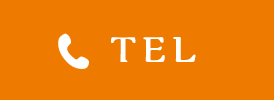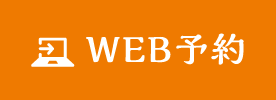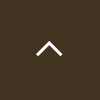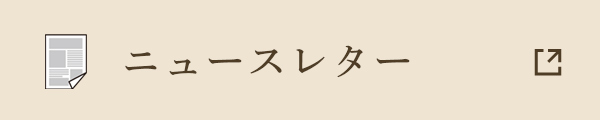心療内科
- HOME
- 心療内科
当院の心療内科 3つのポイント
- 患者さまのお話を、特に生活背景を中心として詳しくお伺いする
- 患者さまと相談しながら、ご自身に相性のよいお薬や用量を見つける
- お薬はあくまで補助的なものと考え、生活習慣や考え方の改善にともに取り組む

現代の医学では、当たり前のように「精神医学」と「身体医学」に分かれております。
ただ総合内科医として長年多くの患者さまと向き合っているうちに、精神と身体を分けることの弊害を感じ、「心」も体の中の「ひとつの臓器」として考えることで様々な問題が見え、そして解決することがわかりました。
病は気からという言葉は昔からありますが、気持ちによって病がつくられてしまうこともあれば、逆に病によって気持ちが落ち込んでくることもあります。これを完全に分けて診療することはおかしなことですね。したがって当院では「内科医」が「精神医療」を行います。
※初診は30分以上の診療枠となりますため、お電話で予約をお取りください。
※当院は労災指定医療機関ではございません。
※初診は高校生以上を対象としております。
※診察後、必要に応じて診断書を即日発行いたします(診断書の種類によっては数日いただくこともあります)。

守秘義務について
受診する際、ちょっとした勇気が必要かもしれません。私たちは患者さまを否定することは決していたしません。
守秘義務はもちろん、診察室内もプライバシーが保たれているので安心です。個人の情報はたとえ家族であっても漏らすことはありません。
また、心療内科以外の患者さまも多数いらっしゃるので、「心療内科に来ていると思われてしまう…」という心配も不要です。
当院の心療内科診療の「ゴール」について
とにかく絶好調でなにもかもがうまく行っている、幸せで満ち溢れているという状態をすべての人に求めるのは難しいと考えています。
結局はありのままの自分を受け入れ、大好きな自分や大嫌いな自分すべてをひっくるめて、これでOK!と思えるような状態になることが大切です。他人と比較するのではなく、他人から悪影響を受ける必要もありません。
自分の過去を変えることはできませんが、自分の考え方、受け止め方、そして在り方は変えることができます。
今この瞬間を自分なりに光り輝き、未来に向かってマイペースで進んでいくお手伝いをする、それが当院の目指す診療のゴールです。

お薬の使用について
薬による治療に抵抗がある方もいるでしょう。逆に、なんでもいいからよくなる薬がほしいという方もいるかもしれません。
当院では基本的に薬物療法を行いますが、あくまで回復のきっかけを与える補助的なものであると理解してください。
はじめは不安があるかもしれませんが、慎重に相談しながら薬の調節を行うことで、薬漬け状態は100%回避できますし、よくなれば治療は終了できます。
当院では使い続けてよい薬、なるべく使わない方がよい薬をはっきりと区別します。使わないほうがよい薬とは、「ベンゾジアゼピン系」の薬(以下ベンゾ)です。睡眠薬、抗不安薬としてよく処方されてしまう薬なのですが、依存や耐性の問題があり、さらに高齢者の場合は筋弛緩作用で転倒のリスクが高くなります。当院では、ベンゾは原則的に常用させないというスタンスをとっています。極端な話、ベンゾを使っている限り病気は治りません。とくにうつ病の治療には病気と向き合う、自分と向き合うことがとても大切になってきますが、ベンゾは病気や自分からの「逃避」に拍車をかけてしまいます。このように、副作用の観点からも、治療の観点からもベンゾは必要最低限に留め、常にいかに減らすかということを考えます。
こんな症状でお悩みではありませんか?
眠れない ― 睡眠薬に頼りすぎない、根本原因へのアプローチ
「なかなか寝つけない」「夜中に何度も目が覚める」「朝早く目が覚めてしまう」
こうした不眠の悩みを抱える方が、近年とても増えています。
不眠は単なる「睡眠の問題」ではなく、心身の状態や生活背景が深く関わっていることが多いため、当クリニックではまず、眠れなくなった背景や原因を丁寧にお伺いすることから始めます。
睡眠薬はすぐに処方しません
初診で「とりあえず睡眠薬を出す」ということはいたしません。
ストレス、生活リズムの乱れ、身体の病気、不安やうつ状態など、不眠にはさまざまな要因があります。そのため、まずは患者さまの生活や心理的な状態を把握し、原因に応じたアプローチを大切にしています。
必要と判断した場合にのみ薬を処方しますが、その際も以下のような点を重視しています。
- 睡眠薬が本当に必要かどうかを慎重に判断
- 数ある薬の中から、その方にとって最も安全で適切なものを選択
- 依存性の強い薬は原則として使用を避ける方針
眠りの質を改善するために
薬だけに頼らず、睡眠習慣の見直しやストレスマネジメント、必要に応じた心理療法や生活指導など、総合的なサポートを行っていきます。
不眠は「眠れるようになること」がゴールではなく、「日中の生活が楽になること」「心が落ち着くこと」が大切です。
「もう何年も眠れない」「睡眠薬をやめたいけどやめられない」
そうしたお悩みも、ぜひ一度ご相談ください。
不眠の背景に寄り添いながら、根本から整えていく治療をご提案いたします。
うつ症状 ― こころの重さに静かに寄り添う診療を
「何をしても楽しいと感じない」「朝、起きるのがつらい」「頭が働かず、ミスが増えた」
このような感覚に心当たりがある方は、もしかすると“うつ症状”が背景にあるかもしれません。
うつ症状は、心の病気のひとつとして知られていますが、実際には「こころ」と「からだ」の両面に影響を与える全身の病気です。たとえば、
-
・疲れやすくなった
-
・食欲が落ちた/逆に過食ぎみになった
-
・寝つきが悪い、朝早く目が覚める
-
・肩こりや頭痛が続く
-
・仕事や家事への意欲が湧かない
といった、一見すると身体的な不調のような形で現れることもあります。
「性格の問題」ではありません
うつ症状は決して「気の持ちよう」や「甘え」ではありません。
生まれ持った気質や、これまでの環境、過剰なストレス、ホルモンや脳内物質の変化など、複数の要因が重なり合って発症するものです。
そのため、まずは患者さまがどのような状況で、何を感じ、どのように日常を過ごしているのか――
お話をじっくり伺いながら、丁寧に背景を整理することを重視しています。
治療はその方の「今」に合わせて
当院では、以下のようなステップで診療を進めています:
-
・詳しい問診と心理状態の把握
-
・必要に応じた血液検査や心理検査(希望に応じて)
-
・休息・環境調整のアドバイス
-
・薬物療法(必要な場合)とその丁寧な説明
-
・心理カウンセリングやストレス対処法の提案
抗うつ薬などの薬を使用する場合は、効果や副作用、生活への影響をしっかり説明した上で開始します。特に初めての方には不安も多いため、安心して治療を受けられるよう、わかりやすい言葉でのご説明を心がけています。
自分を責めずに、ご相談ください
「こんなことで受診していいのかな?」と迷われる方も少なくありません。
しかし、症状が深刻になる前に、早めにご相談いただくことが、回復への第一歩です。
うつ症状は、適切な治療と支えによって、少しずつ回復していくことができます。
ご自身の気持ちや日常の変化に気づかれたときは、どうぞ安心してご相談ください。
強い不安感 ― 理由のわからない不安にも、確かな理解と対処を
「理由はよくわからないけれど、不安でたまらない」
「突然、動悸や息苦しさに襲われることがある」
「常に最悪のことを考えてしまって、疲れてしまう」
このような“強い不安感”に悩まされている方は少なくありません。
不安は誰にでもある自然な感情ですが、日常生活に支障をきたすほどになると、それは治療の対象となる状態です。
不安には、心と体の両方のサインが表れます
不安が高まると、以下のような症状が現れることがあります:
・動悸・発汗・息苦しさ・震え
・胃の不快感や吐き気
・頭が真っ白になる、集中できない
・何度も確認しないと気が済まない
・寝つけない、眠ってもすぐに目が覚める
これらは、心の不調が身体的な症状としてあらわれる典型的な例です。
「不安の正体」を一緒に見つけていきます
当クリニックでは、症状だけを診るのではなく、患者さまがどんな場面で、どんな気持ちになり、不安がどのように現れているのかを丁寧にお伺いし、背景や要因を探っていきます。
・過去の経験やトラウマ
・職場や家庭のストレス
・性格傾向(几帳面さ、責任感の強さなど)
・身体の不調との関連(甲状腺疾患、自律神経の乱れなど)
これらを踏まえ、薬に頼りすぎず、必要最小限の治療で改善できるよう心がけています。
必要に応じた薬の処方も、丁寧にご説明します
強い不安には抗不安薬や抗うつ薬などの薬物療法が有効な場合もありますが、当院では、
・依存性のある薬は慎重に取り扱うこと
・「今の状態に本当に必要かどうか」を常に見極めること
・ご本人の希望を尊重し、副作用や効果をしっかり説明すること
を大切にしています。
「心配しすぎ」「気にしすぎ」などと言われて、自分でも自分の不安を責めてしまう方が多くいらっしゃいます。
ですが、不安を感じること自体は、決して弱さではありません。
それは「助けが必要なサイン」です。
そのサインに耳を傾けながら、自分らしく安心して過ごせる日々を一緒に取り戻していきましょう。
パニック障害 ― 突然の強い不安発作に悩まされていませんか?
「突然、強い動悸や息苦しさに襲われる」
「めまいや手足の震えが出て、『このまま死んでしまうのでは』と感じる」
「また発作が起きるのではと怖くなり、外出ができなくなった」
このような経験がある方は、パニック障害の可能性があります。
パニック障害は、明確なきっかけがないまま突然“パニック発作”が起こる病気で、脳の不安系が過敏になっている状態と考えられています。
多くの方は、「身体の病気かもしれない」と内科などを受診されますが、心療内科的なアプローチが必要になるケースも多くあります。
当院では、まず身体の状態をしっかり確認した上で、必要に応じて心のケアにつなげる方針をとっています。
薬物療法や心理療法を組み合わせ、発作への恐怖を和らげ、安心して日常生活を送れるようサポートしていきます。
社交不安障害(対人緊張) ― 人と関わる場面で極度に緊張してしまう方へ
「人前で話すと声が震える」「視線が怖い」「常に人にどう思われているか気になってしまう」
このような症状は、社交不安障害(または社交不安症・対人恐怖症)と呼ばれる状態かもしれません。
この症状は、単なる“あがり症”や“恥ずかしがり屋”とは異なり、日常生活や仕事・学業に支障をきたすほどの強い不安や緊張が継続する点に特徴があります。
・発表や会議の場面で極度に緊張してしまう
・食事中、字を書く場面などで視線が気になり避けてしまう
・人との関わりを避け、孤立を深めてしまう
といったことに悩む方は非常に多く、自己否定感や抑うつ状態を伴うことも少なくありません。
当院では、こうした対人場面での不安に対して、その方の不安の構造を丁寧に把握し、薬物療法・心理療法のいずれか、または両方を併用しながら、少しずつ自己肯定感と行動範囲を広げていく支援を行っています。
ストレスや疲れ(不定愁訴)
- とにかく体の調子が悪く、いろいろな精密検査をしたけれども異常がないと言われ、それ以上診察してくれなかった。
- 異常な疲労感、めまい、あちこちの痛み、耳鳴り、頭痛、腹痛、喉の違和感、しびれ、口の渇き、動悸、胸の痛み、吐き気など、いわゆる「不定愁訴」と言われてどの病院に行っても原因不明で治らないと言われてしまった。
なんらかのストレスや疲れが、体の症状に姿を変えてでてきている可能性が考えられます。
ストレスなんてないと思っていても、ただ気づかずに蓄積され、自律神経を乱すことで、様々な症状として自覚することも多々あります。
心療内科的な視点で診察、治療をすることで、症状の緩和が期待できます。
認知症
- ものの在りかがわからなくなる
- 食事したことを忘れる
- 新しいことが覚えられない
- 道に迷う
- 火のつけっぱなし
- いないはずの人が見える
物忘れが気になり、認知症かな?と心配になった際には受診してください。適切な診断と治療を行いますが、残念ながら認知症は治癒する病気ではありません。認知症の進行を緩やかにする薬はありますので、症状に応じて適切な治療薬の選択をいたします。
むしろ私たちが得意とする場面はいわゆる認知症の「周辺症状」でお困りのときです。おばあちゃんの被害妄想がひどく、家族に攻撃的になってしまう。おじいちゃんが昼夜の区別がつかず、夜中に眠らずに家族の生活がめちゃくちゃになってしまっている。このような場合、お薬による対応で本人もご家族も穏やかに過ごせるようになります。
また、認知症の対応で重要なのは適切な介護サービスを利用することです。介護サービスを利用するには介護保険が必要となります。要介護認定を受けていない方は、主治医として意見書をお書きしますのでご相談ください。
一方で、認知症の症状が、別の疾患によって生じることもあります。この場合、認知症も「治る」可能性があります。本当に物忘れが認知症なのか、あるいは他に病気が隠れていないかということを、内科医の視点からしっかりと見極めるところから始めます。
注意欠如/多動性障害(ADHD)
- 仕事などでケアレスミスが目立つ
- すぐに気が散って集中できない
- 学業や仕事での義務をやり遂げることができない
- 忘れ物、なくし物が多い
- 約束を忘れる
- 仕事や家事を順序だてて進められない
- 物事を2つ以上同時に行う事が苦手
- 片付けが苦手
- じっとしているのが苦手
- 貧乏ゆすりなど、目的のない動きが多い
- 順番を待つことができない
これらの事は幼少期から見られましたか?その場合は、ADHDの可能性があります。
ADHDは、病気ではありません。あなたの「個性」のひとつです。ただ、その個性のせいで日常生活や仕事に支障がでていると感じた場合にはご相談ください。あなたのコンディションを整えるお薬を用いて、本来の能力を発揮するお手伝いができます。
初診と診療の頻度について
初診について
- 初回診察は30分ほどいただきます。
- 診察前に詳しい問診票をご記載いただきます。
- 必要に応じて血液検査をいたします。
2回目以降の診療の頻度について
- 2、3回目は1週間前後で受診していただきます(患者さまのご都合に合わせます)
- それ以降は状態に応じて受診間隔を決めます。
- 次回予約以前に具合が悪くなった場合など、適宜早めに受診していただくことも可能です。
※当院は藤沢市にほど近い場所にありますので、藤沢市にお住いの方も通院に便利です。夜は18時まで診療で、駐車場もございます。
精神科デイケアについて
同じ奏愛会内で展開している大船心療内科のデイケアへご紹介させていただきます。
精神科訪問看護について
当院と連携しているアカラ・ケア訪問看護ステーションへご紹介させていただきます。